〒194-0022 東京都町田市森野1-31-18 シェア・プラザ101
小田急線町田駅北口徒歩4分
受付時間 | 8:45~17:15 |
|---|
定休日 | 土日 |
|---|
孫への贈与優遇制度始まる
祖父母が孫に教育資金をまとめて贈る場合、1500万円までは贈与税をかけない制度が2013年4月から2015年12月までの期間限定で始まりました。祖父母がみんなで孫一人あたり1500万円まで非課税で教育資金を贈与できます。信託銀行などに専用口座をつくり入金しておき、必要な時には、教育資金かどうかがわかるように領収書などを銀行に示す必要があります。30歳に達した時点で口座に残額があれば、その分には贈与税が課税されます。概要は次のとおりです。
・期間 2013年4月〜2015年12月
祖父母が孫一人当たり1500万円の教育資金を事前に贈ることができる

・非課税になるもの → 最大1500万円
幼稚園・小中高校・大学・専修学校・高等専門学校など学校向けの授業料や教材の支払い
例 授業料・入学金・冷暖房などの施設の使用料・修学旅行・遠足費
うち学校以外に支払う費用 → 最大500万円
例 学習塾や予備校・習い事(英会話や習字、そろばん、楽器や踊り、絵画、スポーツなど)の学
費
・非課税にならないもの
・下宿代、留学先への渡航費(学校に支払わない場合)
・楽器の購入
・本屋での参考書の購入
詳細は信託銀行に聞いて確認し利用しましょう
厚生年金61歳からの受給開始
会社勤めの人の厚生年金の支給開始年齢が本年2013年4月から61歳になり、今後10年以上かけて65歳に引き上げられます。会社員が加入する1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金に分かれています。1階部分がもらえるのはすでに65歳からになっています。2階部分はこれまで60歳から受け取れたが、2013年4月以降、男性は61歳にならないともらえなくなります。女性も、5年後の2018年4月から61歳からになります。65歳より前に年金をもらう「繰り上げ受給」という方法もありますが、デメリットが多いので慎重にした方がよいです。 年金の受取額が減ります。1カ月早めるとごとに年金額は0.5%ずつ減り、65歳から受け取る年金を60歳まで繰り上げてしまうと、30%もの減額になってしまいます。減額された年金は、一生涯続きます。 また60から64歳の間に障害を負ったときはには通常、障害年金がもらえますが、支給を繰り上げるとその時点で受給資格を失うことになり、万が一の場合に受けられなくなってしまいます。

厚生年金支給開始年齢の引き上げ(男性の場合)
対象となる人の誕生日 支給開始年齢・厚生年金(報酬比例部分) 基礎年金
1953年4月2日〜55年4月1日 61歳 既にに65歳
1955年4月2日〜57年4月1日 62歳
1957年4月2日〜59年4月1日 63歳
1959年4月2日〜61年4月1日 64歳
1961年4月2日以降 65歳
女性は5年遅れで引き上げがはじ始まります。
変わる老後の生活設計に注意を
2015年1月から相続税の基礎控除額が縮小(予定)
2013年度の税制改正改正大綱では、2015年1月から亡くなった人が残した現金や預金、不動産などの遺産に相続税がかかりますが、遺産のうち税がかからない「基礎控除額」が縮小されます。現在は「5千万円+法律に基づいて相続する人の数(法定相続人)×1千万」でしたが、これを「3千万+法定相続人×600万」に縮小される予定です。
例 夫が亡くなり法定相続人が妻と子供2人の場合
改正前 5000万円+1000万円×3人法定相続人の数=8000万円(基礎控除額)
↓
改正後 3000万円+ 600万円×3人法定相続人の数=4800万円(基礎控除額)
*相続した財産が「基礎控除額」を超えると相続税が発生します。
一方、課税対象者が大幅に増えることに対応した緩和措置として、遺産額を計算する際の自宅の土地のの評価額を最大8割減額する「小規模宅地」の上限を240平方メートル(約73坪)から330平方メートル(100坪)に拡大される予定です。

小規模宅地等の特例緩和
例 1億円の土地であれば2000万円として評価
対象面積 現行240㎡まで → 330㎡まで
特例を受ける相続人の条件
・配偶者
・同居、生計を同じにしている親族
・持家のない別居している親族
相続税税対策をいまから考えておく必要がありますね、
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
改正高齢法が4月からスタート
65歳まで働きたい人全員が働けるようにする「改正高齢者雇用安定法(高齢法)」が2013年4月から施行されました。改正高齢法は、65歳までの希望者全員の雇用確保を企業に義務づけています。企業には、
・定年の廃止
・定年の引き上げ
・再雇用制度の導入
という三つの選択肢があります。

厚生労働省の2012年「高年齢者の雇用状況」によると約8割の企業が取り入れているのが再雇用制度です。これまでは労使で決めた再雇用基準を満たさないと判断され、希望しても再雇用されない人がいましたが、今後は希望者全員が60歳以降も働けるようになります。ただし、給与水準はそれまでの50〜70%程度になるのが一般的なので、60歳以降も働く場所はあるけれども所得は下がります。また再雇用の条件が合わなくて退職を選んだり、再雇用後は1年更新の契約社員になる場合が多いため雇い止めにあう恐れも生じます。
いずれにせよ厳しい雇用状況にあります。 高齢者の皆さん頑張ってください。
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
建設業許可申請提出書類・確認資料の追加(社会保険関係)
建設業の社会保険加入推進の一環として、建設業法施行規則等の改正が行われました。(平成24年5月1日公布)。これを受け、次にとおり新たな取り組みがスタートしました。
・平成24年11月1日より、許可申請書に保険加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。
・国、都道府県の建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施します。
・目的・・・
建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない企業(社会保険未加入企業)が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。
このため、関係者を挙げた社会保険未加入問題への対策の一環として、建設業の許可に際しての社会保険加入状況の確認・指導を進めることにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図ることを目的としています。
・社会保険加入義務のある営業所(適用事業所)とは・・・
健康保険・厚生年金保険については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
・建設国保に加入している場合は・・・
法人の営業所又は個人経営で5人以上の労働者を使用する営業所であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外となります。

建設業に係る協会けんほへの加入と国民健康保険組合への加入について
医療保険への加入については、地域の建設企業のうち、常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会が運営する健康保険(通称「協会けんぽ」)に事業所として加入することが健康保険上求められているが、協会けんぽの被保険者とならない5人未満の従業員を使用する事業主や一人親方などであって、現在既に建設業に係る国民健康保険組合に加入している者については、既に必要な健康保険に加入しているものとして取り扱われるものであり、社会保険未加入対策上改めて協会けんぽに入り直すことを求めているものではありません。
なお、法人や常時5人以上の従業員を使用している事業者が建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合もあるが、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した際、あるいは、常時使用する従業員が5人以上に増加した際に、必要な手続き(年金事務所(平成22年以前は社会保険事務所)による健康保険被保険者適用除外承認申請による承認)を行って加入しているものであれば、適法に加入しているものであります。年金制度は厚生年金に加入し、医療保険制度は国民健康保険組合に加入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入り直すことを求める必要はありません。
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて
「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」平成25年2月5日に国土交通省土地・建設産業局建設業課長から通知がでております。
建設業法(以下、「法」という。)第26条、建設業法施行令(以下、「令」という。)第27条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という)については、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第315号。以下、「制度運用マニュアル」という。)により、その適正な配置をお願いしてきたところであり、また、現場代理人については、公共工事標準請負契約約款(以下、「標準約款」」という。)において、常駐義務緩和に関する規定が設けられているところですが、今般、その取扱い等を下記のとおり定め、地方整備局等あて通知しましたのでお知らせします。
また、「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」(平成24年2月20日付け国土建第265号)は、廃止します。
1.令27条第2項の当面の取扱いについて
令27条第2項においては、同条第1項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意されたい。
(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が5㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令27条第2項が適用される場合に該当すると判断して差し支えない。
(2) (1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。
(3)(1)及び(2)の適用にあたっては、法26条第3項が、公共性のある施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。

2. 現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について
平成22年7月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(標準約款第10条第3項)が追加されたことを受け、「現場代理人の常駐義務緩和に関する適正な運用について」(平成23年11月14日付け国土建第161号)において、適切な運用に努めるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、当該規定の趣旨を踏まえ、現場代理人の常駐義務緩和について適切に運用されたい。
なお、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第26条第3項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和されるものではないことに留意されたい。
3.監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について
監理技術者等の専任を要しない期間については、制度運用マニュアルのほか、「主任技術者又は監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について」(平成21年6月30日付け国総建第75号)において、適切に設定されるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ」、監理技術者等の専任を要しない期間について適正に運用されたい。
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
改正特定商取引法による「訪問購入」の規制
2012年8月に改正された特定商取引法が2013年2月21日から施行されました。今まで訪問購入には次のようなトラブルが起きています。
1.悪質な勧誘
・突然の訪問による強引な買取りの勧誘。
・断ってもしつこい。
・「着物を買う」と電話がかかってきたが、実際は「指輪を売ってくれ」と言われた。
2.契約内容や事業者の連絡先が分からない
・売ったものを返してほしいけど、連絡先が分からない。
・何を買い取られたのか記憶が曖昧になってしまい、事業者と交渉しにくい。
3.一度引き渡すと、原状回復は難しい
返してもらおうと思ったら、もう溶かしたと返事が・・・・。
4.クーリング・オフができなかった
契約後、すぐクーリング・オフを申し入れたが、「買取りの場合はクーリング・オフできない。」「キャンセル料がかかる。」と言われれた。
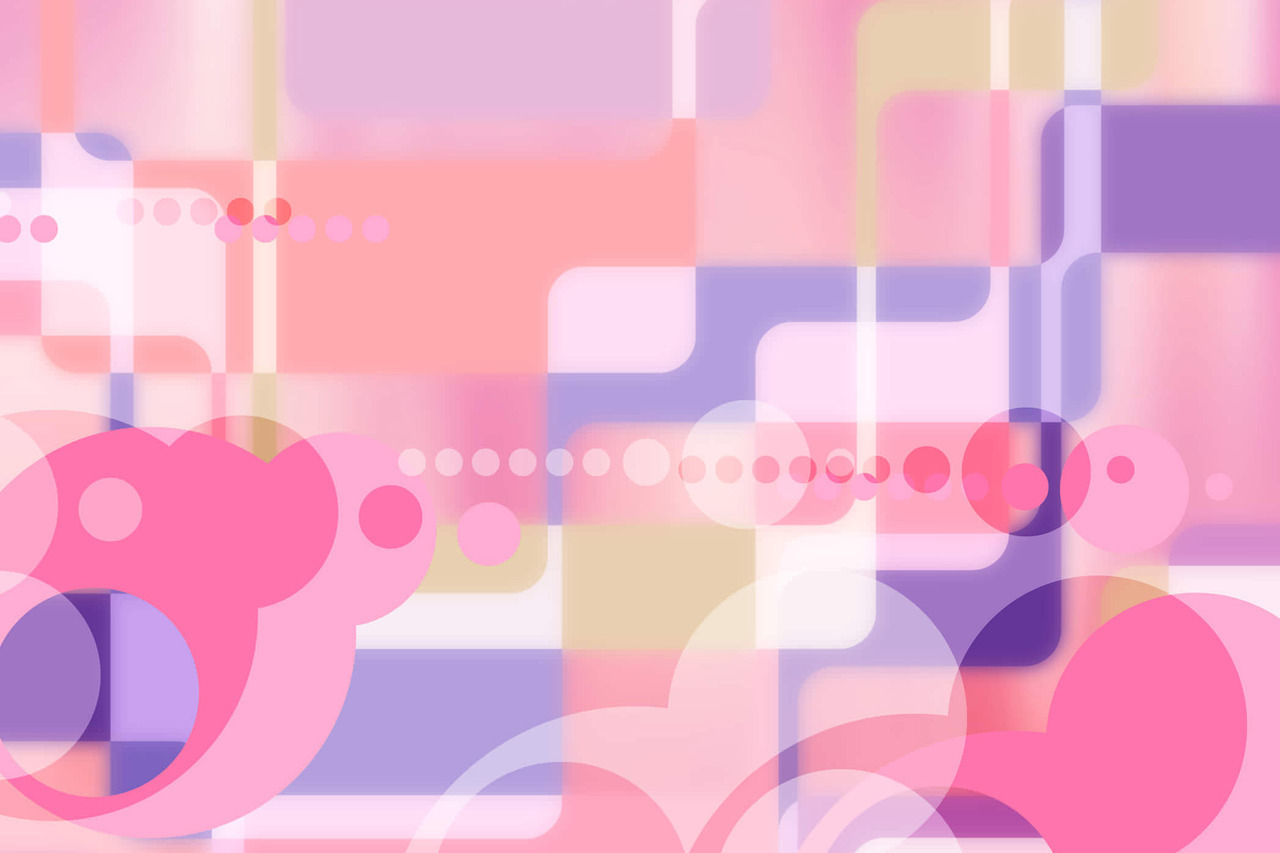
法律の改正で、次のように変わります。
1.不招請勧誘の禁止
・訪問購入で飛び込みの勧誘はできなくなりました。消費者から査定に関してのみ訪問要請を受けた場合も、査定を超えた勧誘行為は禁止となります。
・また、しつこい勧誘や、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止となります。
2.書面の交付
事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面が交付されます。
3.引渡しの拒絶
クーリング・オフ期間中(2.の書面交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことができます。また、事業者は迷惑を覚えさせるような方法で引渡しをさせること等も禁止されています。
4.クーリング・オフ
クーリング・オフ制度により、2.の書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。また、クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合、その情報が事業者からすぐに通知されます。
ただし、以下の物品と取引態様は規制の対象となりません。
・ 自動車(2輪のものを除く。)
・ 家具
・ 家電(携行が容易なものを除く。)
・ 本、CDやDVD、ゲームソフト類
・ 有価証券
・ 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
・ いわゆる御用聞き取引の場合
・ いわゆる常連取引の場合
・ 転居に伴う売却の場合
* 再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。
消費者庁の消費者ホットライン
0570−064−370
2013年4月1日から小型家電リサイクル法が運用開始
2012年8月に公布された小型家電リサイクル法が2013年4月1日から施行されました。
小型家電リサイクルの対象品目
・ パソコン ・ 携帯電話 ・ ドライヤー ・ DVDプレーヤー、、
・ デジタルカメラ ・ 時計 ・ 電子辞書 など....
この他にも電子レンジや掃除機など100品目以上の小型家電が対象です。市町村ごとに回収品目が異なります。
*テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目は、、これまでどおり「家電リサイクル法」の対象です。「小型家電リサイクル法」の対象ではありません。
1. なぜ小型家電を集めてリサイクルするのか、
資源の有効利用と環境汚染防止のためです。小型家電には、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有効な金属が含まれています。しかし、現在まで鉄などの一部の金属を除いて、その大半が廃棄物の埋立地に処分されています。また、違法な不用品回収業者を通じて国内外で不適正な処分が行われているものもあります。
2.どのように回収するか、
・ ボックス回収 ・ ピックアップ回収 ・ ステーション回収
3.個人情報が入っている携帯電話やパソコンはきちんと取り扱われるか、
適正な管理の下、回収・リサイクルが行われます。
4.回収されたものはどうなるか、
きちんと処理され、資源となります。
適正なリサイクルを実施する者として国の認定を受けた「認定事業者」が、回収された小型家電を分解・破砕し、金属の種類やプラスチックごとに選別し、金属精錬事業者が金属資源として、再生します。この過程で有害物質も処理します。消費者から回収された小型家電は、リサイクルされ、再び製品として還ってきます。
5.いつから回収がスタートするか、
2013年4月1日以降、回収体制の準備ができた市町村から順次、回収を開始します。
6.違法な不用品回収業者が集めたものはどうなるの、
国内外での不適正処理につながっています。
認定事業者
・再資源化のための事業を行おうとする者は、再資源化事業の実施に関する計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることができます。要件の例として、(1)適切かつ継続して再資源化を行えるような経理的基礎を有すること(2)対象とする区域が隣接する3都道府県(北海道及び沖縄を除く)以上の区域、かつ、その区域の人口密度が1,000人/k㎡未満であること、といったようなものがあります。

| 家電リサイクル法 | 小型家電リサイクル法 | |
| 対象品目 | テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目 | 携帯電話、デジタルカメラ、ゲームなど多数*具体的に回収・リサイクルする品目は市町村ごとに決定 |
| 使用済み家電の回収方法 | 家電販売店(小売業者)が消費者から回収し、製造メーカーがリサイクル | 市町村が回収ボックスや回収コンテナなどを設置して回収*回収方法は市町村ごとに定められる*家電量販店(小売業者)も回収に協力 |
| 再資源化の実施 | 製造メーカー | 認定事業者など(確実・適切なリサイクルの実施について国が認定した事業者) |
| 消費者の費用負担 | 対象品目によって数千円程度を負担+運搬料金 | 市町村によって異なり、品目によっては手数料がかかる場合がある |
改正犯罪収益移転防止法が2013年4月1日から施行
1.犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。(2008年3月1日施行)
2.改正犯罪収益移転防止法の概要 (2013年4月1日施行)
〇 取引時の確認事項の追加(士業者を除く)
一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。
・ 取引を行う目的
・ 職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
・ 実質的支配者(法人)
・ 資産及び収入の状況(ハイリスク取引の一部)
〇 ハイリスク取引の類型の追加
マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引(ハイリスク取引)の類型を定め、厳格な方法による確認の対象とされました。
〇 取引時確認等を的確に行うための措置の追加
事業者は、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育等の必要な体制の整備に努めなければなないこととされました。
〇 特定事業者の追加
電話転送サービス事業者について、新たに特定事業者に追加することとされました。
〇 罰則の強化
本人特定事項の虚偽申告、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則が強化されることとされました。

確認が必要な事業者と確認が必要な取引
| 確認が必要な事業者 | 確認が必要な取引 |
| 金融機関等 | ・預貯金口座等の開設 ・200万円を超える大口現金取引 ・10万円を超える現金送金 など |
| ファイナンスリース事業者 *リースがすでに保有している物品を顧客に賃貸するものは、法律の対象外です。 | 一回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結 |
| クレジットカード事業者 | クレジットカード契約の締結 |
| 宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介 |
| 宝石・貴金属等取扱事業者 | 代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 |
| 郵便物受取サービス業者(私設私書箱) | 役務提供契約の締結 |
| 電話受付代行業者(電話秘書) | 役務提供契約の締結 *電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結は除く。 *コールセンター業務等の契約の締結は除く。 |
| 新規事業者 電話転送サービス事業者 | 役務提供契約の締結 |
| 司法書士 行政書士 公認会計士 税理士 | 以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結 ・宅地または建物の売買に関する行為または手続き ・会社等の設立または合併等に関する行為または手続き ・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分 *租税、罰金、過料等の納付は除く。 *成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。 *任意後見契約の締結を除く。 |
| 弁護士 | *司法書士等の他の士業者の例に準じて、日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。 |

取引時の確認事項とその書類
| 確認事項 | 通常の取引 | ハイリスク取引 | |
| ① | 本人特定事項(氏名・住所・生年月日(個人)/名称・所在地(法人)) | 以下の本人確認書類 (個人) ・運転免許証、運転経歴証明書 ・健康保険証 ・国民年金手帳 ・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの) ・旅券(パスポート) ・在留カード、特別永住者証明書など
(法人) ・登記事項証明書 ・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)など | 通常の取引に際して確認した書類+上記以外の本人確認書類 |
| ② | 取引を行う目的 | 申告 | 通常の取引と同じ |
| ③ | 職業(個人の場合) | 申告 | 通常の取引と同じ |
| 事業内容(法人の場合) | 定款、登記事項証明書など | ||
| ④ | 実質的支配者(25%を超える議決権を有する者 等) | 該当の有無 | |
| 申告 | 株主名簿、有価証券報告書など | ||
| 本人特定事項 | |||
| 申告 | 本人確認書類 | ||
| ⑤ | 資産及び収入の状況(ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る) | ー | (個人の場合) 源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳など (法人の場合) 貸借対照表、損益計算書など |
◎有効期限のある書類の場合、事業者が提示または送付を受ける日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、事業者が提示または送付を受ける日の前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
◎士業者は①のみについて確認をおこないます。
ハイリスク取引時の確認
マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(ハイリスク取引)を行う際に、厳格な確認が必要です。
また、当該取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産及び収入の状況の確認も必要です。(士業者を除く)。
ハイリスク取引とは
なりすましが疑われる取引等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、以下に該当する取引を言います。
・過去の契約の際に確認した顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引。
・過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引。
・イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引。
国民年金保険料の後納制度
平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を10年前まで納めることができます
老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年を満たしていることが必要となります。それに満たない場合は、老齢年金を受け取る資格が得られなくなってしまいます。また、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳〜60歳までの40年間、、国民年金に加入し、保険料をきちんと納付していることが必要で、保険料を納めなかった期間があると、その分、受け取る年金額が少なくなります。
また、期限までに納めていない保険料があると、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても障害年金や遺族年金が受給できない場合もあります。
国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料については、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(「後納制度」といいます。)
この後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
対象者は早めに手続きをしてください。

・対象者
後納制度を利用できるのは、次のような方です。
(1)20歳から60歳未満の方で、過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方
(2)60歳以上65歳未満の方で(1)の期間のほか、任意加入期間(*)に保険料の納め忘れがある方
(3)65歳以上の方で、(1)の期間のほか、任意加入期間(*)に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格がない方
*国民年金の加入期間は原則として20〜60歳までですが、老齢年金の受給資格期間(原則25年)が足りない場合は70歳まで、年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで、国民年金に任意加入することができます。
・納付保険料額
| 対象年度 | 25年度中に後納する場合の1ヵ月分の保険料額(加算額を含む。加算額は毎年度改定されます。) |
| 2003年度(平成15年度) | 14,860円 |
| 2004年度(平成16年度 | 14,640円 |
| 2005年度(平成17年度 | 14,690円 |
| 2006年度(平成18年度 | 14,750円 |
| 2007年度(平成19年度 | 14,780円 |
| 2008年度(平成20年度) | 14,890円 |
| 2009年度(平成21年度) | 14,970円 |
| 2010年度(平成22年度) | 15,240円 |
| 2011年度(平成23年度) | 15,020円 |
・後納制度を利用できる期間
平成24年10月1日〜平成27年9月30日(3年間)
・申込方法
平成24年8月1日〜平成27年9月30日までに、「国民年金後納保険料納付申込書」に必要事項を記載して、年金事務所に申し込みます。
国民年金保険料専用ダイヤル 0570−011−050
改正労働契約法
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が対象となります。
改正法の3つのルール
Ⅰ 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
Ⅱ 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
Ⅲ 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
施行期日
Ⅱ :平成24年8月10日(公布日)
ⅠとⅢ:平成25年4月1日

Ⅰ 無期労働契約への転換(第18条)
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新されて場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換します。
通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。
無期転換の申し込みができる場合
(契約期間が1年の場合の例)
← 5年 →
1年 →1年 →1年 →1年 →1年 →1年 →③無期労働契約
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
締結 更新 更新 更新 更新 ④更新 ①申込 ②転換
→1年 →1年 ③無期労働契約
↑ ↑ ↑
④更新 ①申込 ②転換
通算5年を超えて契約更新した労働者が、
その契約期間中に無期転換の申し込み
をしなかったときは、次の更新以降でも
無期転換の申し込みができます。
(契約期間が3年の場合)
← 5年 →
3年 →3年 →③無期労働契約
↑ ↑ ↑ ↑
締結 ④更新 ①申込 ②転換
① 申込・・・平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申し込みをすることができます。
② 転換・・・無期転換の申し込み(①)をすると、使用者が申し込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約(③)がその時点で成立します。無期に転換されるには、申し込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
①の申し込みがなされると③の無期労働契約が成立するので、②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇は権利濫用に該当するものとして無効となります。
③ 無期労働契約・・・無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前に有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。
「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。
なお、無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。
④ 更新・・・無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。

通算契約期間の計算について(クーリングとは)
空白期間の前はカウントに含めず
←ーーーーーーーー → ← 5年 →
1年 →1年 →1年 →・・・・・・・・・1年 →1年 →1年 →1年 →1年 →1年
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
締結 更新 更新 ⑤6か月以上の 更新 更新 更新 更新 更新 申込可能
空白期間
⑤ 空白期間・・・有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。これをクーリングといいます。
通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があればそれ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。
Ⅱ 「雇止め法理」の法定化(第19条)
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」といいます。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。今回の法改正は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化されました。
| 対象となる有期労働契約 | 次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約が対象になります。 ① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの ② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由(*)があると認められるもの (*)1.合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。 2.いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに合理的な理由の存在が否定されることにはならないと解されます。 |
| 要件と効果 | 上記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。 |
| 必要な手続き | 条文化されたルールが適用されるためには、労働者からの有期労働契約の更新の申し込みが必要です(契約期間満了後でも遅滞なく申し込みをすれば条文化されたルールの対象となります)。 ただし、こうした申し込みは、使用者による雇止めの意思表示に対して、「嫌だ、困る」と言うなど、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもかまわないと解いされます。 |
Ⅲ 不合理な労働条件の禁止
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。
| 対象となる労働条件 | 一切の労働条件について、適用されます。 賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます。 |
| 判断の方法 | 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、 ① 職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度) ② 当該職務の内容および配置の変更の範囲 ③ その他の事情 を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。 とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記①〜③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されます。 |
認知症の高度障害保険金の受給
生命保険に加入する認知症の人が、「高度障害」と認められ、保険金を受け取れることがあります。どんな状態が高度障害にあたるかは、多くの保険会社が同様の目安を設けています。
高度障害 : 生命保険に入っている人が、病気やけがが原因で、約款で定める「高度(重度)障害」と認められた時、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
認知症の人は「3」の「終身常に介護を要する」に当たる可能性があります。まれに「2」の「言語の機能を全く永久に失った」に当てはまることもあります。しかし、実際に常に介護が必要でも、高度障害と認められるとは限りません。
現役世代が認知症を発症すると、家計が打撃を受けることも多く、高度障害保険金を請求する人が増えてきています。
通常、高度障害保険金を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって契約は消滅し、それ以降の特約等の給付金は受け取ることができません。
高額療養費制度について
1.高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベット代等は除く。)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
<例>
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
← 医療費 100万円 →
← 窓口負担 30万円 →
↑ ↑ →
↑ 高額療養費として支給 30万円ー87,430円=212,570円
負担の上限額 80,100円+(1,000,000円ー267,000円)×1%=87,430円
212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。
2.負担の上限額は、年齢や所得によって異なる
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられています。70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
<70歳以上の方の場合>
| 所得区分
| 1か月の負担の上限額 | 1か月の負担の上限額 | |
| 外来 | |||
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費ー267,000円×1% | |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者(住民税非課税の方) | Ⅱ(Ⅰ以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方) | 15,000円 | ||
(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含む。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
<70歳未満の方の場合>
| 所得区分 | 1か月の負担の上限額 |
| 上位所得者(月収53万円以上の方など) | 150,000円+(医療費ー500,000円)×1% |
| 一般 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |
| 低所得者(住民税非課税者の方) | 35,400円 |
(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含む。)では上限額をこえないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

3.「世帯合算」及び「多数回該当」
高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。
(1)世帯合算
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれ支払いになった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
被保険者A 世帯合算
甲病院 自己負担額
60,000円 世帯合算後の
(医療費 : 200,000円) 自己負担額
乙薬局 自己負担額 ||
24,000円 60,000円
(医療費 : 80,000円) +24,000円
被扶養者B +30,000円
丙病院 自己負担額
30,000円 =114,000円 → 高額療養費の支給対象となる
(医療費 : 100,000円)
(2) 多数回該当
直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
<70歳以上の方の場合>
所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当の場合
現役並み所得者 80,000円+(医療費ー267,000円)×1% 44,400円
(注) 「一般」や「低所得者」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
<70歳未満の方の場合>
所得区分 本来の負担の上限額 多数回該当の場合
上位所得者 150,000円+(医療費ー500,000円×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費ー267,000円×1% 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円

4.「所得区分」の認定証
入院される方についは、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払いを負担の上限額までにとどめることもできます。このため、一度に用意する費用が少なくて済みます。
*高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
*70歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払いが負担の上限額までにとどめられます(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。
<100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
通常の場合
入院される方
①医療費の3割 ②高額療養費の ↑ ③高額療養費
(30万円)を 支給申請 (約20万円)
支払い ↓ ↓ の支給
病院 加入する医療保険
所得区分の認定証がある場合
入院される方
①一定の限度額 ②高額療養費 ↑ ③高額療養費の
(約9万円) の請求 (約21万円)
を支払い ↓ ↓ の支給
病院 加入する医療保険
一度に用意する
費用が安くて済む
改正精神保健福祉法
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が改正され平成26年4月1日から施行されます。
統合失調症、うつ病など心を病んだ人や認知症の人を、治療の必要がある場合に、本人の意向に係らず入院させる「医療保護入院」という制度があります。これまでは親や配偶者などが「保護者」となり、同意する必要がありましたが、来春から三親等までの親族なら誰でも同意できるようになります。
1.改正の趣旨
精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針の策定、保護
者制度の廃止、医療保護入院における入院手続き等の見直し等を行う。
2.主な改正の要点
(1)保護者制度の廃止
主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の
高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。
現在の法律では、医療保護入院及び退院の同意は「保護者」です。保護者になれるのは1人で優
先順位は決まっている。
①成年後見人 ②配偶者 ③ 親権者 ④ 扶養義務者 ⑤ 該当者がいない場合等市町村長
扶養義務者が保護者になるときは家庭裁判所で選任を受ける必要がある。
ほとんどは三親等以内の親族が担っているのが現状です。
(2)医療保護入院の見直し
医療保護入院における保護者の同意を外し、家族等(*)のうちいずれかの者の同意を要件とする。
*配偶者、親権者、扶養義務者、成年後見人、該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断
扶養義務者の家庭裁判所の選任を受ける必要はない。

生活保護法
1.生活保護制度
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給され
る保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
2.制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的
な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
3.相談・申請窓口
生活保護の相談・申請窓口は、現在住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事
務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。福祉事務所を設置していない
町村に住まいの方は、町村役場でも申請の手続きを行うことができます。
4.生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
(1)保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その
最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法
による保護に優先します。
・資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費にあてます。
・能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働きます。
・あらゆるものの活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用します。
・扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けます。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最
低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
(2)支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない
場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
支給される保護費=最低生活費 ー 年金、児童扶養手当等の収入
収入としては、就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助等を認定します。
最低生活費= ① 生活扶助基準(第1類費)+ ② 生活扶助基準(第2類費)+
③ 加算額(障害者、母子世帯等、子供養育費)+
④ 住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等

(3)保護の種類と内容
以下のように、生活を営むうえで必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
| 生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
| 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費) | 生活扶助 | 基準額は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
| アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
| 医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払い(本人負担なし) |
| 介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払い(本人負担なし) |
| 出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活扶助基準額の例(平成24年4月1日現在)
| 東京都区部等 | 地方郡部等 | |
| 標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 172,170円 | 135,680円 |
| 高齢者単身世帯(68歳) | 80,820円 | 62,640円 |
| 高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 121,940円 | 94,500円 |
| 母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 192,900円 | 157,300円 |
*児童養育加算を含む。
5.生活保護の手続きの流れ
(1)事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当を訪問 します。生活保護制度の説明を受けるとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について 検討します。
(2)保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査が実施されます。
生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
預貯金、保険、不動産等の資産調査
扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
就労の可能性の調査
(3)保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費と して毎月支給されます。
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告することが必要です。
世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
6.相談・申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保 障施策の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産の状況がわかる資料(通帳の写しや 給与明細書等)を提出する場合があります。

婚外子相続規定は憲法違反
2013年9月4日、最高裁大法廷は、非嫡出子側が嫡出子と同じ割合での相続を求めていた遺産分割事件において、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であると定める民法第900条4号但し書きの規定が法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する、との初判断を示しました。
本決定の主な要旨は次のとおりです。
1.1947年の民法改正後、婚姻、家族の形態は著しく多様化し、国民の意識の多様化も大きく進んだ。現
在、嫡出子と非嫡出子の相続分に差異を設けている国は、世界的にも限られている状況だ。国連の委員
会は、差別的規定を問題にして」、法改正の勧告等を繰り返してきた。
2.法律婚という制度自体は定着しているとしても、父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選
択、修正する余地のないことを理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重
し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている。
民法の婚外子の相続規定は、遅くても本件の相続が開始した2001年7月当時、立法府の裁量権を考慮
しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的根拠は失われており、規定は憲法14条に違
反していたというべきだ。
3.本決定は、1995年の決定やその後の小法廷の判決等が、2001年7月より前に相続が開始した事件に
ついて、その相続開始時点の規定を合憲とした判断を変更するものではない。
他方、本決定の違憲判決が、すでに行われた遺産分割にも影響し、解決済みの事案にも効果が及ぶとす
ることは、著しく法的安定性を害することになるから、すでに裁判や合意で確定した法律関係まで現時点で
覆すことは相当でない。2001年7月から本決定までの間に開始された他の相続で、確定的となった法律
関係に影響を及ぼすものではないとするのが相当だ。

出生届の「婚外子」記載規定
2013年9月26日、最高裁第一小法廷は、結婚した男女間に生まれた嫡出子(婚内子)かどうかを出生届に記すよう義務づけた戸籍法の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、「規定は差別的扱いを定めたものではなく、憲法には違反しない」との初判断示す一方、「記載の義務づけが、事務処理上不可欠とはいえない」とした。
戸籍法第49条第2項1号は、出生届に「嫡出子」か「嫡出でない子」(婚外子)かを記載すると定めている。出生届には「嫡出子」「嫡出でない子」のチェック欄がある。戸籍法が出生届に婚内子・婚外子の記載を求めているのは、親が結婚しているかどうかで、遺産相続や子の名字などの扱いに違いが生じるためだ。
婚内子の場合、名字は両親と同じだが、婚外子は原則として母親の名字を名乗り、認知されない限り法律上の父親は決まらない。
2013年9月4日、婚外子の民法の相続規定が違憲となり見直される以上、戸籍法の規定も見直される可能性がある。

認知症男性(夫)の徘徊中の事故は「妻に責任」(名古屋高裁判決)
愛知県大府市で2007年12月、認知症の男性(夫・当時91歳)が徘徊中、JR東海道線共和駅の構内で列車にはねられて死亡した。男性は「要介護4」と認定されていて、日常的な介護は、自らも「要介護1」と認定されていた同居する妻(当時85歳)と介護のため近くに転居してきた長男の妻があたっていた。事故当日、男性は部屋で二人きりだった妻がうとうとする間に外出していた。
JR東海は、列車の遅れに伴う振り替え輸送費などの損害賠償を求めていた。
昨年8月の名古屋地裁の判決は、妻については、長男が決めた方針の中で、男性と二人きりの時に目を離さずにいる義務を負っていたのに怠った。長男は、横浜市に住み、男性の介護方針を決めていて事故を防ぐ責任があったと認定。徘徊し事故に遭う可能性を予測できたのに、見守りを強める責任を果たさなかったと判断した。妻と長男にそれぞれ約720万円の支払いを命じた。
これに対し、名古屋高裁判決は、相当前から長男は、男性と別々に暮らしていて、経済的な扶養義務があったに過ぎず、介護の責任を負う立場になかったとして、長男への請求を退けた。一方、妻については、民法上、配偶者として男性を介護・監督する義務があったと判断した。高齢だったものの、家族の助けを受けていて、男性を介護する義務を果たせないとは認められないと判断した。ただ、充実した介護態勢を築き義務を尽くそうと努力していたこと、JRにはフェンスに施錠したり、駅員が乗客を注意深く監視したりしていれば事故を防ぐことができたとして、賠償金額は、地裁の5割が相当として、約359万円とした。
認知症の人の数は急増している。認知症の介護は誰にとってもでくわす問題である。家族に責任があるという判決は厳しいものがある。

自転車利用の安全とマナー(2013年12月1日からルール変更)
道路交通法上、自転車は自動車と同じ車両の一種の「軽車両」です。法律など決められたルールは守らなければなりません。歩道では、歩行者優先を忘れてはなりません。
1.2013年12月1日から施行
(1) 左側通行が新ルール
道路交通法の一部改正により、自転車で道路路側帯を通行する場合、道路の右側にある路側帯を
走ることが禁止されました。
これまで路側帯は双方向で通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるた
め、自転車などの軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られるこ
とになりました。
(2) ブレーキの検査
警察官がブレーキ装置のない自転車を停止させて検査を行ったり、応急のブレーキ整備や運転継
続の禁止を命じることができるようになりました。
2.違反な乗り方
(1) 飲酒運転
(2) 信号無視
(3) 一時不停止
(4) 遮断踏切立ち入り
(5) 携帯電話使用運転
(6) 傘差し運転
(7) イヤホーン等使用運転
(8) 夜間の無灯火運転
(9) 二人乗り運転
(10) 並進通行
(11) 歩道での歩行者妨害
3.万が一の事故に備えて
自転車で走行中、不意に転倒した場合、頭を道路に強打する危険があります。13歳未満の子供に
ル
メットをかぶせることはもちろん、大人もヘルメットなどの交通事故による被害を軽減する器具の利用に努
めることが必要です。
4.自転車事故で高額な賠償を命じた判決例
最近は自転車事故の加害者側に高額な賠償を命じる判決が相次いでいる。
自転車を運転中に散歩中の女性と接触し、寝たきり状態にさせてしまった小学生の親に裁判所が命じ
た賠償額は約9500万円(一審・神戸地裁)であった。
| 年 | 賠 償 額 | 判 決 | 内 容 |
| 2013 | 約9500万円 | 神戸地裁 | 小学5年の男児が散歩中の女性と衝突。障害が残るけがを負わす |
| 2008 | 約9300万円 | 東京地裁 | 男子高校生が歩道から車道を斜めに横断。男性と衝突。障害が残るけがを負わす |
| 2007 | 約5400万円 | 東京地裁 | 男性が信号無視して交差点に進入し、横断中の女性と衝突。死亡させる |
| 2005 | 約5000万円 | 横浜地裁 | 女子高校生が夜間、無灯火で歩行中の女性と衝突。障害が残るけがを負わす |
| 2003 | 約6800万円 | 東京地裁 | 男性がペットボトル片手に交差点に進入し、横断中の女性と衝突。死亡させる |
自転車の場合保険に加入している人は少ない。しかし、いざ事故を起こすと深刻な事態に陥ることも十分ありうる。もしもの場合に備え、自転車保険の加入も視野に入れておくと安心である。
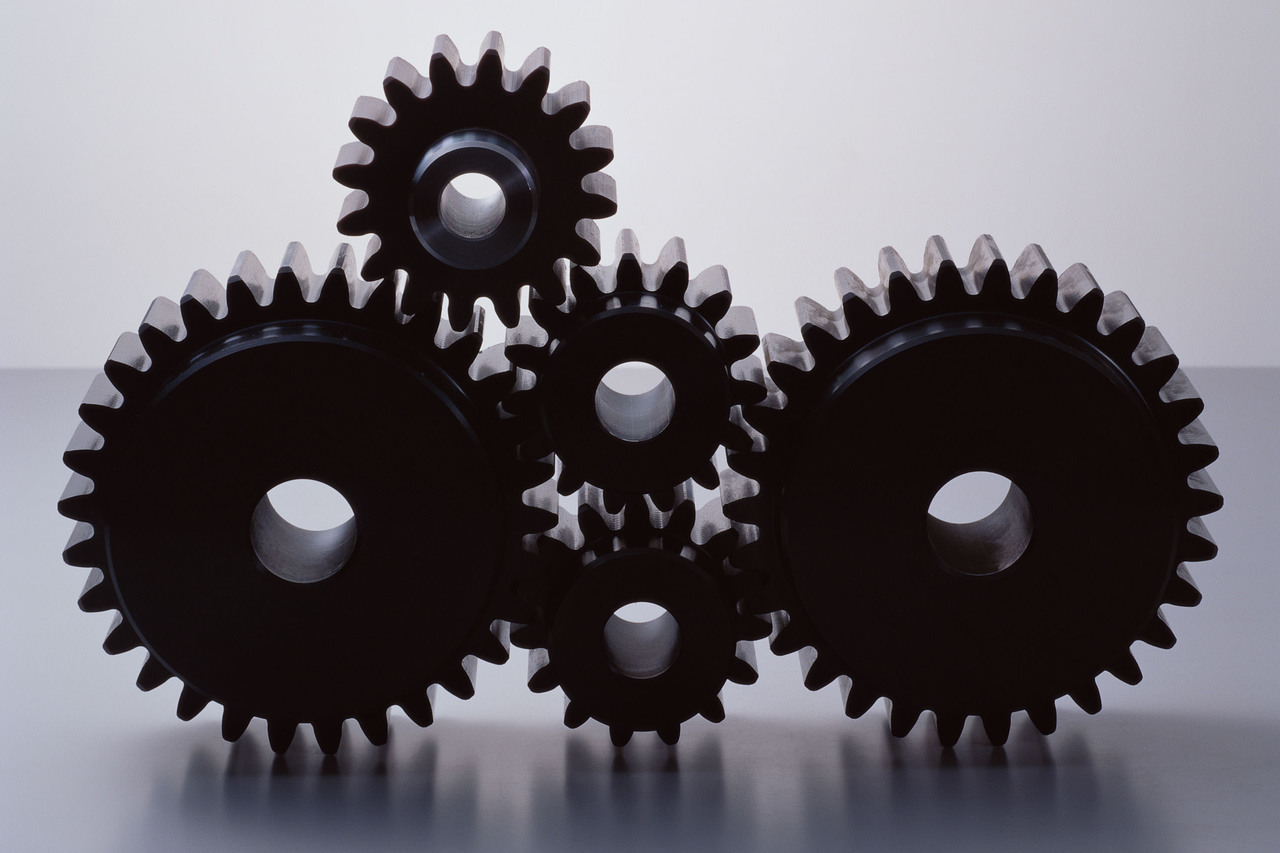
建設業における社会保険について
1.建設業における社会保険について
建設業では、下請を中心に、法令によって加入が義務付けられている健康保険、厚生年金、雇用保険について、企業の未加入、労働者の未加入などによって、法定福利費を適正に負担しない未加入企業が存在しています。
社会保険などへの未加入は、技能労働者の処遇の低下など就労環境を悪化させ、若年入職者が減少する一因となっています。
本来は法律上加入する義務のある保険未加入の企業は、必要経費を負担していないため、その分コストがかからず、競争上は有利ということになります。
こうした状況が建設業における社会保険の問題であります。
2016年度までに行政と業界が一体となって取り組むことによって、2017年度には加入義務のある許可業者の100%の加入を目指しています。
2.社会保険
国民皆保険として法律で国民に加入が義務付けられている保険制度には、医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険があります。
建設業の場合、労災保険は原則として元請が一括して加入する方法が一般的ですが、医療、年金、雇用は、企業ごとに加入することになっています。しかし、建設業の場合、下請を中心に企業の未加入、労働者の未加入が存在しています。
3.労働者
保険によるさまざまな給付は、加入することによってはじめて利用することができます。給付のための費用は、加入する労働者が負担する保険料はもちろんですが、事業者が負担する保険料(法定福利費)、さらに公の税金も投入されています。
保険料の支払いはたしかに負担ではありますが、失業や老後の無収入、病気の時の高額な医療費負担に備えるためにも、社会全体で支えあう保険に加入しておくことが必要です。
4.経営者
保険の加入は法令上の義務となっています。大切な従業員のことを考えれば、加入は企業の責務であり、保険料の事業主負担分(法定福利費)は、企業としてどうしても負担しなければならない経費です。
建設業に若年者が安心して入職できるようにするうえで、社会保険などの福利厚生を見直して就労環境を改善することは、企業として建設業の将来にとっても必要不可欠です。

5.建設業における労働保険、社会保険
| 労働保険 | 社会保険 | 事業主負担計(賃金に対する比率) | |||||
| 事業所の形態 | 常用の労働者の数 | 就労形態 | 雇用保険 | 労災保険 | 医療保険(事業主負担には介護保険を含む) | 年金保険 | |
| 法人 | 一人〜 | 常用労働者 | 雇用保険(事業主負担1.05%) | 元請一括加入(下請の事業主負担なし) | 協会けんぽ、健康保険組合等(事業主負担5.76%) | 厚生年金(事業主負担8.533%) | 3保険の負担15.343%) |
| ー | 日雇労働者 | 日雇労働保険(事業主負担1.05%+48〜88円) | 元請一括加入(下請の事業主負担なし) | 国民健康保険)又は協会けんぽ(日雇特例被保険者)(国保は事業主負担なし、日雇特例被保険者の事業主負担日額240円から1995円 | 国民年金(事業主負担なし) | 日雇労働保険の負担1.05%+日額48〜88円 | |
| ー | 役員等 | ー | 特別加入(事業主負担あり) | 協会けんぽ、健康保険組合等(事業主負担5.76%) | 厚生年金(事業主負担8.533%) | 2保険+労災保険の負担14.293%+労災保険料 | |
| 個人事業主 | 5人〜 | 常用労働者 | 雇用保険(事業主負担1.05%) | 元請一括加入(下請の事業主負担なし) | 協会けんぽ、健康保険組合等(事業主負担5.76%) | 厚生年金(事業主負担8.533%) | 3保険の負担15.343% |
| 1〜4人 | 常用労働者 | 雇用保険(事業主負担1.05%) | 元請一括加入(下請の事業主負担なし) | 国民健康保険(事業主負担なし) | 国民年金(事業主負担なし) | 雇用保険の負担1.05% | |
| ー | 日雇労働者 | 日雇労働保険(事業主負担1.05%+日額48〜88円 | 元請一括加入(下請の事業主負担なし) | 国民健康保険又は協会けんぽ(日雇特例被保険者)(国保は事業主負担なし、日雇特例被保険者の事業主負担日額240円〜1995円) | 国民年金(事業主負担なし) | 日雇労働保険(事業主負担1.05%+日額48〜88円 | |
| ー | 事業主、1人親方 | ー | 特別加入(事業主負担あり) | 国民健康保険(事業主負担なし) | 国民年金(事業主負担なし) | 労災保険料の負担 | |
6.社会保険等加入指導状況(平成24年11月〜平成27年3月)
| 申請等 | 指導 | 加入 | 通報 | 加入確認待ち | ||||||
| 申請等件数 | 既加入件数 | 既加入率 | 指導件数 | 指導率 | 加入件数 | 加入率 | 通報件数 | 通報率 | 件数 | 比率 |
| 310,413 | 271,236 | 87.4% | 39,177 | 12.6% | 13,710 | 35.0% | 18,080 | 46.1% | 7,387 | 18.9% |
| 26年9月時点 265,445 | 232,490 | 32,955 | 11,326 | 14,037 | 7,592 | |||||
改正建設業法(平成27年4月1日)
平成27年4月1日から、改正建設業法が施行されました。
解体工事業の新設については、平成28年春頃施行予定
1.許可(更新)申請書や添付書類が変わります。
(1)必要書類が追加されます。
・従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要とな
ります。
・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
(2)書類が簡素化されます。
・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要とな
ります。
・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
(3)営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になります。
2.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます。
(1)型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
(2)建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。
3.施工体制台帳の記載事項が追加されます。
(1)外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。
(再下請通知にも記載が必要)
4.暴力団の排除が徹底されます。
(1)役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が
含まれいる法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を支配されている者につい
ては、許可を受けられなくなります。また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになりま
す。
5.許可申請書等の閲覧制度が見直されます。
(1)個人情報が閲覧対象から除外されます。
(2)大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。

→ お問い合わせはこちら → 目次にもどる
改正入管法(平成26年6月18日)
改正入管法が平成26年6月18日に公布されました。改正の主なポイントは次のとおりです。
1.在留資格の整備
(1)在留資格「留学」が付与される方の範囲を中学生や小学生まで広げる。
2015年(平成27年)1月1日〜
学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学校、小学校の留学生にも在
留資格「留学」が付与されます。
(2)高度外国人のための新たな在留資格「高度専門職」を創設
2015年(平成27年)4月1日〜
高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在
留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材の方を対象とした新たな
在留資格「高度専門職第1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、
活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職第2号」を設けます。
なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続
き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことがで
きます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職第1号」の在留資格を経るこ
となく、直接、「高度専門職第2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
(3)在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ変更
2015年(平成27年)4月1日〜
日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の
「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくし
ました。これにより、国内資本企業の経営・管理」を行うことも同在留資格によってできるようになります。
(4)在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化
2015年(平成27年)4月1日〜
専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務
に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留
資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。
2.上陸審査の円滑化に向けた手続を新設
2015年(平成27年)4月1日〜
(1)クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査手続について円滑化を図る。
法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める「船舶観光上
陸許可」制度を設けます。
また、航空機で入国し「短期滞在」の在留資格を与えられた外国人が、我が国から他国に渡って我が国
に戻る航路のクルーズ船に乗り、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合(いわゆるフライ・アン
ド・クルーズの場合)には、原則として再入国許可を要しないものとします。
(2)信頼できる渡航者について、出入国手続の円滑化を図る。
2016年(平成28年)末〜
自動ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前
に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上、問題を生じるおそれが少ないと認めら
れて登録したものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の
証印に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)を設けます。

改正介護保険法(平成27年4月から)
介護保険法が平成27年4月から改正されました。主要な改正点は次のとおりです。
平成27年4月から
●低所得者の保険料軽減が拡充されました。(一部実施)
低所得者の保険料に軽減措置が設けられ、標準の負担割合で最大限軽減した場合、第1段階の方の負担割合は基準額の0.45に軽減されます。また、所得水準に応じた保険料の標準の段階が6段階から9段階に変わりました。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
| 所得段階 | 対象者 | 保険料額 |
| 第1段階 | ・世帯全員が区市町村民税非課税で、生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が区市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.5(平成27、28年度0.45)(平成29年度0.3) |
| 第2段階 | 世帯全員が区市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.75(平成29年度0.5) |
| 第3段階 | 世帯全員が区市町村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 | 基準額×0.75(平成29年0.7) |
| 第4段階 | 本人が区市町村民税非課税だが、課税されている人が世帯にいる方で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 |
| 第5段階 | 本人が区市町村民税非課税だが、課税されている人が世帯にいる方で、第4段階に該当しない方 | 基準額 |
| 第6段階 | 本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 |
| 第7段階 | 本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.3 |
| 第8段階 | 本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 | 基準額×1.5 |
| 第9段階 | 本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が290万円以上の方 | 基準額×1.7 |
| *第1段階から第3段階の方には、介護保険法に基づく保険料の軽減があります。(第1段階の方は、平成27年度から対象になります。第2段階、第3段階の方は、平成29年度から対象になります。) *表中( )内の負担割合は、最大限の軽減をした場合になります。 | ||
●介護老人福祉施設の入所基準が変わりました。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象となりました。特別養護老人ホームの入所を希望しているにもかかわらず、在宅生活を続ける重度の要介護状態の方が多数おります。そのような方が、優先的に入所できるよう見直すことにしたものです。
ただし、要介護1や2の方特例的に入所できるのは、以下のような考慮事項を勘案して特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情がある場合です。
① 認知症で、日常生活に支障を期すような症状等が頻繁に見られること
② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を期すような症状等が頻繁に見られること
③ 深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
④ 単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること
平成27年8月から
●一定以上の所得がある方は利用者負担が変わります
一定以上の所得がある方は、サービスを利用した時の利用者負担が2割になります。
2割負担になる人は、65歳以上の方で、合計所得金額(*1)が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)
ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯(*2)で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(*3)」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
*1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
*2 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
*3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
●介護保険負担割合証が発行されます
区市町村から利用者の負担割合(1割又は2割)が記載された介護保険負担割合証が発行されます。
●低所得者の利用者が負担する食費・居住費の軽減の適用条件が変わります
低所得者の利用者のうち、配偶者が住民税課税者である場合又は預貯金等が一定額を超える場合には、食費・居住費の軽減がなくなります。
① 配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外とする(世帯が同じかどうかは問わない)
② 預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外とする
配偶者がいる方 :合計2,000万円
配偶者がいない方 :1,000万円
なお、①又は②に該当して負担軽減の対象外となった方でも、その後該当しなくなった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。
●特養の相部屋(多床室)に入所する市区町村民税課税世帯の方の部屋代負担
室料相当を負担していただく対象者は、特別養護老人ホームに入所する方、ショートステイ(短期入所生活介護、予防短期入所生活介護)を利用する方のうち、相部屋(多床室)に入所しており、食費・部屋代の負担軽減を受けていない方が対象になります。
●月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方の負担の上限は37,200円です。特に所得の高い現役並み所得相当の方がいる世帯の方については、44,400円(月額)に引き上げられます。
引き上げの対象者は、同一世帯内に課税所得(*1)145万円以上の65歳以上の方がいる場合に対象になります。ただし、
・同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合 :その方の収入が383万円未満
・同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる)場合 :それらの方」の収入の合計額が520万円未満
である場合には、その旨を市区町村にあらかじめ申請することで37,200円になります。
*1 「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
| 区 分 | 負担の上限(月額) | ||
| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯)*<新設> | ||
| 世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 37,200円(世帯) | ||
| 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | ||
| ・老齢福祉年金を受給している方 ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人)* | ||
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | ||
*「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。
●平成28年4月から
小規模な通所介護が地域密着型サービスに移ります(平成28年4月開始)
定員18人以下の小規模な通所介護が、「地域密着型通所介護」として、地域密着型サービスへ移ります。
●平成29年4月から
低所得者の保険料軽減の拡充が完全実施になります
標準の負担割合で最大限軽減した場合、第1段階の方は基準額の3割、第2段階の方は5割、第3段階の方は7割の負担に軽減されます。
以 上

→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
解体工事業(改正建設業法 平成28年6月1日)
1.解体工事業の新設に伴う経過措置
(1)平成28年6月1日の改正建設業法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体
工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の
許可を受けずに解体工事を施工することができます。
その後も解体工事業を営む場合、平成31年5月末までに解体工事業の許可を追加申請す
る必要があります。
(2)平成28年6月1日の改正法施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者として
の経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
(3)解体工事の内容、例示、区分の考え方
| 解体工事の種類 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 | 建設工事の区分の考え方 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て 以下略 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の楊重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 以下略 | 現行のとび・土工・コンクリート工事の区分の考え方のうち、下記解体分を除いたものが該当する |
| 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。 |
| 解体を伴う新設 | 解体のみ | |||
| 各専門工事で作ったもの 例:信号機を解体して同じものを作る | 土木一式工事・建築一式工事で作ったもの 例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る | 各専門工事で作ったもの 例:信号機を解体して更地にする | 土木一式工事・建築一式工事で作ったもの 例:一戸建て住宅を壊して更地にする | |
| H28 5/31以前 | 各専門工事で施工 例:電気工事業 | 土木一式工事・建築一式工事で施工 例:建築一式工事業 | とび・土木工事で施工 | とび・土木工事で施工 |
| H28 6/1以降 | 各専門工事で施工 例:電気工事業 | 土木一式工事・建築一式工事で施工 例:建築一式工事業 | 各専門工事で施工 例:電気工事業 | 解体工事で施工 |
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
執行役員等の経営業務の管理責任者への追加等(平成28年6月1日)
1.執行役員等の経営業務の管理責任者への追加
(1)概要
「業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建
設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な
権限委譲を受けた執行役員等」に改正
(2)範囲
「執行役員等」については、許可を受けようとする個々の業種区分の建設業について、それ
ぞれの建設業に関する「事業部門全般の業務執行に係る権限委譲」を受けている必要があ
ります。
(3)確認書類
① 組織図その他これに準ずる書類
② 業務分掌規程、過去の稟議書その他これに準ずる書類
③ 定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締
役会議事録その他これに準ずる書類
2.建設業法上の金額要件の見直し
(1)特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ
建築一式工事以外 3,000万円 → 4,000万円
建築一式工事 4,500万円 → 6,000万円
(消費税込)
(2)専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負金額の引き上げ
建築一式工事以外 2,500万円 → 3,500万円
建築一式工事 5,000万円 → 7,000万円
(消費税込)
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
経営業務の管理責任者の要件の改正(平成29年6月1日)
1.経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者配置、契約締結等の業務全般に従
事した経験(保佐経験)の一部拡大
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管理責任者に準ずる
地位にあって資金調達、技術者配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」が位
置付けられており、この「準ずる地位」については、現在「業務を執行する社員、取締役又は執
行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)」が位置付けられているところです。この点、
「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経
験として認めることとする。
2.他業種における執行役員経験の追加
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の執行に関して、取
締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に
基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」が位置付けられている。
この点、現在は、「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られているところ、「許
可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認めることとする。
3.3種類以上の合算評価の実施
経営業務管理責任者要件として認められる経験(現行4種類)については、現在、一部種類に
ついて2種類までの合算評価が可能とされているところです。この点、全ての種類に拡大する
とともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することを可能とする。
4.他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の
建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、現在7年以上要することと
しているが、これを6年に短縮することとする。あわせて、2の経験及び経営業務を補佐した
経験についても、同様に6年とする。
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
再婚禁止期間及び花押は無効
再婚禁止期間の短縮(平成28年6月7日)
1.女性の再婚禁止期間が、従前の6か月から、前婚の解消又は取り消しの日から起算して100日
に短縮された。
2.女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合、又は女性が前婚の若
しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用しないこととなった。
戸籍事務の取扱い
1.「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱い
(1)民法第733条第2項に該当する旨の証明書
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは、再婚をしようとしている本人である
女性を特定する事項のほか、①本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後
に懐胎してしていること、②同日以後の一定の時期において懐胎していないこと、③同日以
後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいう。
なお、医師の診察を受ける際、「前婚の解消又は取消日」(離婚日など)を申告する必要
がある。
この日について誤って別の日を申告した場合には、本証明書を作成してもらったとして
も、再婚禁止期間の再婚が認められない場合がある。
(2)届出の受理
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚
姻の届出について、上記の「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、
「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消
又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には、その他の婚姻要件を
具備している限り、その届出は受理され、婚姻することが可能となる。
(3)戸籍の記載
(2)の届出が受理されると、妻の身分事項欄に婚姻事項とともに「民法第733条第
2項」による婚姻である旨が記載されることとなる。
2.「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付が添付されていない婚姻の届出の取扱い
前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の
届出に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない場合には、民法第
733条第1項の規定が適用されることとなるため、婚姻の届出は受理されない。
ただし、これまで証明書がなくても再婚禁止期間内にされた婚姻の届出について受理されて
いた類型(前婚の夫と再婚する場合など)については、今後も証明書がなくても婚姻の届出は
受理される。
花押を記した遺言書は、無効(平成28年6月3日)
最高裁第二小法廷は、「花押」を記した文書が遺言書として有効かどうかが争われた訴訟の上告
審判決で、「花押」は印章による押印と同視できず、民法第968条第1項の押印の要件を満た
さないと判断し、遺言書として有効とした2審判決を破棄した。
本事案は、琉球王国の名家の末裔(えい)にあたる沖縄県の男性が、平成15年に死亡する前
に作成した文書(3人兄弟のうち、「財産は次男を家督相続人として継承させる」と記し、末尾
に花押が記されていた)の有効性を争うもので、1,2審は「花押の方が押印よりも偽造が困難」
とし、遺言書として有効と判断しました。
しかし、最高裁は、「遺言書に押印を必要とする理由は、印を押すことによって重要な文書の
作成を完結するという慣行や意識が社会の中にあることがその一つである」が、「押印に代えて
花押を書くことで文書を完成させるという慣行や意識は存在しない」と指摘した。
なお、今回の判決は、印鑑の代わりに指印(拇印)を押した遺言書の効力が争われた平成元年
2月16日最高裁判決(第一小法廷)を引用している。この判決は、「遺言書に押印を必要とす
る理由は、印を押すことにより重要な文書の作成を完結するという慣行や意識が社会の中にある
ことがその一つである」ことを指摘したうえで、「指印(拇印)を印鑑の代わりに用いる慣行が
社会一般に存在する」ことを根拠として、遺言書を有効と判断した。これに対し、今回の判決
は、「花押を印鑑の代わりに使用して文書を完成させるという慣行や意識が社会の中にあるとは
言えない」とし、遺言を無効と判断したことで、「指印(拇印)と「花押」とでは、使用される
頻度が異なることから、平成元年判決と同じ判断基準に基づいて、全く逆の結論を導いたことに
なった。
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
法定相続情報証明制度(平成29年5月29日)
平成29年5月29日から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が施行され、これに伴い不動
産登記事務等の取扱いについて新たな制度が登記所(法務局)において開始されました。「法定相続
情報証明制度」です。
制度の概略
1.申出の流れ(法定相続人又は代理人)
(1)戸除籍謄本等を収集
(2)法定相続情報一覧図の作成
(3)申出書に必要事項を記載し(1)、(2)の書類を添付して登記所に申出
① 代理人になれるんは親族又は各仕業
② 申出をすることができる登記所は被相続人の本籍地・被相続人の最後の住所地・申出人
の住所地・被相続人名義の不動産の住所地、いずれかの地を管轄する登記所
③ 申出は登記所の窓口に直接提出するか、郵送によって行う
| 被相続人法務太郎法定相続情報 最後の住所 〇県〇市〇町〇番地 住所 〇県〇郡〇町〇番地 出生 昭和〇年〇月〇日 出生 昭和〇年〇月〇日 死亡 平成〇年〇月〇日 (子) (被相続人) 法務一郎 法務太郎 住所 〇県〇市〇町〇番地 出生 昭和〇年〇月〇日 住所 〇県〇市〇町〇番地 (子) 出生 昭和〇年〇月〇日 相続紀子 (配偶者) 法務花子 住所 〇県〇市〇町〇番地 出生 昭和〇年〇月〇日 (子) 登記進 作成日 〇年〇月〇日 作成者 行政書士 〇〇 〇〇 (住所 〇市〇町〇番地) |
2.確認・交付(登記所)の流れ
(1)登記官による確認、一覧図の保管
(2)認証文付き一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
・交付にあたり、手数料はありません
3.利用
各種の相続手続きへの利用(戸籍謄本の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能
になる)
一旦、戸籍謄本等一式を揃え図面化作業を要する点では現行と同じです。しかし、一覧図の
写しを作成して必要数を用意しておけば、複数の登記所や金融機関での手続きを同時に行いた
い場合に簡便になるメリットがあります。なお、相続放棄や遺産分割協議に関する書類は別途
必要になります。

→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
民法(相続法)の改正、遺言書保管法の制定(平成30年7月)
2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。具体的には、
(1)被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(2)遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
① 自筆証書遺言の方式緩和
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
(3)その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの
改正を行っています。
1.配偶者居住権の新設 2020年4月1日施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
現行制度
配偶者が居住建物を取得する場合は、他の財産を受け取れなくなってしまう。
改正によるメリット
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。
2.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
2019年7月1日施行
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
現行制度
贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
⇒ 被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。
改正によるメリット
このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。
⇒ 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。
3.預貯金の払戻し制度の創設 2019年7月1日施行
預貯金が遺産分割の対象となる場合い、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
現行制度
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。
改正のよるメリット
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設ける。
(1)預貯金債権の一定割合(金額にる上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口のおける支払を受けられるようにする。
(2)預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
4.自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
現行制度
自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。
改正によるメリット
自書によらない財産目録を添付することができる。
5.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について 2020年7月10日施行
制度の概要
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
6.遺言の活用
我が国においては、遺言の作成率が諸外国に比べて低いといわれていますが、今回の改正により、自筆証書遺言の方式を緩和し、また、法務局における保管制度を設けるなどしており、自筆証書遺言を使いやすくしています。
7.遺留分制度の見直し 2019年7月1日施行
(1)遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
(2)遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
現行制度
① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生じる。
⇒ 事業承継の支障となっているという指摘
② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるた
め、通常、分母・分子とも極めて大きな数字となる。
⇒ 持分権の処分に支障が出るおそれ
改正によるメリット
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生じることを回避することができる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。
8.特別の寄与の制度の創設 2019年7月1日施行
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
現行制度
相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができない。
改正によるメリット
相続開始後、長男の妻は、相続人(長女・次男)に対して、金銭の請求をすることができる。
⇒ 介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られる。
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る

自筆証書遺言書保管制度の開始(令和2年7月10日)
令和2年7月10日(金)自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
遺言は、自分が死亡したときに相続人等に対して、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。
これにより相続をめぐる争いを事前に防止することができます。
遺言の方式は主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
この制度は自筆証書遺言が対象です。本制度を利用すると、
・法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。手数料が必要です。
・法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要です。
制度の概要
自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請することができる制度です。保管制度を利用すると遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットがあります。
生前
遺言者
遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管場所)に申請の予約をしてうえで、
直接本人が出向きます。本人以外は申請できません。
法務局(遺言書保管場所)
本人確認、遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等)を外形的に確認等
死亡後
相続人等
① 請求(交付、閲覧)
② 交付 遺言書情報証明書
閲覧
③ 通知
遺言者のメリット
① 紛失・亡失を防ぐことができます。
② 他人に遺言書を見られるkとがありません。
③ 相続人や受遺者等の手続が楽になります。
相続人・受遺者等のメリット
遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続は不要のため、速やかに相続手続ができます。相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、全国の遺言書保管場所で次の手続ができます。
・遺言書保管事実証明書の交付申請
遺言書が保管されているかどうかを調べること
・遺言書情報証明書の交付請求
唯銀所の内容の証明書の交付を申請すること
・遺言書の閲覧請求
遺言書悪寒場所において遺言書の内容を見て確認すること
自筆証書遺言書の作成時の注意事項
本文は、遺言者本人が自書(手書き)しなければなりません。作成年月日、署名押印が必要です。
訂正した場合、訂正部分に押印が必要です。訂正した旨を自書しなければなりません。
目録にも署名押印が必要です。
目録は、パソコンで作成したものや通帳などのコピーでも構いません。
自筆証書遺言書の保管の申請に必要なもの
・自筆証書遺言書(A4版、片面で、とじたり封のされていないもの)
・申請書(法務省指定の様式)
・添付書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)
・手数料(1件につき、3,900円(収入印紙で納付))
自筆証書遺言書の保管の申請先
遺言者の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管場所
遺言書保管の申請をする際は、予約が必要となります。
注意事項
・保管の対象となる遺言書は、どのようなものか
保管の対象となるのは、自筆証書遺言書のみです。遺言書は、用紙の大きさはA4版、片面で、法務省令で定める様式に従って作成され、とじたり封のされていないものでなければなりません。
・遺言書のすべてをパソコンで作成できますか、
遺言書の本文、作成年月日及び氏名は、手書きで作成しなければなりません。自筆証書遺言書に添付する財産目録は、パソコンで作成しても構いませんが、各ページに署名押印が必要です。
・遺言の保管の申請は、郵送や代理でもできますか、
郵送や代理での申請はできません。
・遺言書の保管等に費用はかかりますか、
・遺言書の保管申請(1件3,900円) ・遺言書情報証明書の交付申請(1通1,400円)
・遺言書の閲覧請求(1回1,400円(モニター)、1,700円(原本))
・遺言書保管事実証明書の交付請求(1通800円)

東京法務局管内遺言書保管所管管轄
| 遺言書保管所 | 管 轄 区 域 |
| 本局 電話:03-5213-1441 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域 |
| 板橋出張所電話:03-3964-5385 | 中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区 |
| 八王子支局電話:042-670-6240 | 八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 |
| 府中支局電話:042-335-4753 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市 |
| 西多摩支局電話:042-551-0360 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 |
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日)

相続土地国庫帰属制度
1.概要
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度。
一定の要件を設定し、法務大臣が要件について審査を実施する。
(1)土地の要件 通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地は不可
(2)負担金等 土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理 費相当額の負担金の納付が必要
2.申請権者
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権または共有持分を取得した者等
3.土地の要件
(1)却下要件(その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要す ると扱われるもの)
承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができな い。
① 建物の存する土地
② 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用 悪水路・ため池の用に共されている土地)が含まれる土地
④ 土壌汚染対策法上の特定有害物により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
→ これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しなければなら ない。
(2)不承認要件(費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの)
法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土 地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
① 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、 その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
② 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に 存する土地
③ 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることあできない有体物が地下に存する 土地
④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができ ない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収 益が現に妨害されている土地)
⑤ 通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地
a 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更 に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)
b 鳥獣や病害虫などにより、当該土地または周辺の土地に存する人の生命もしくは身体、 農産物または樹木に被害が生じ、または生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)
c 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
d 国庫に帰属したのち、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担 する土地
e 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する 土地
→ いずれかに該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をする。
4.負担金
(1)宅地
宅地(その現況および従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができ ると認められる土地)のうち、都市計画法7条1項い規定する市街化区域の区域(区域区分 に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法8条1項1号に規定 する用途区域が定められいる土地の区域)
| 地積の区分 | 負担金に係る算定金額 |
| 50㎡以下のもの | 地積に4,070円を乗じて得た額に208,000円を加えて得た額 |
| 50㎡を超え100㎡以下のもの | 地積に2,720円を乗じて得た額に276,000円を加えて得た額 |
| 100㎡を超え200㎡以下のもの | 地積に2,450円を乗じて得た額に303,000円を加えて得た額 |
| 200㎡を超え400㎡以下のもの | 地積に2,250円を乗じて得た額に343,000円を加えて得た額 |
| 400㎡を超え800㎡以下のもの | 地積に2,110円を乗じて得た額に399,000円を加えて得た額 |
| 800㎡を超えるもの | 地積に2,010円を乗じて得た額に479,000円を加えて得た額 |
(2)農地
主に農地(農地法2条1項に規定する農地をいう)として利用されている土地のうち、都市 計画法7条1項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律8条2 項1号に規定する農用地区域内または土地改良法2条2項に規定する土地改良事業若しくは これに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの。
| 地積の区分 | 負担金に係る算定金額 |
| 250㎡以下のもの | 地積に1,210円を乗じて得た額に208,000円を加えて得た額 |
| 250㎡を超え500㎡以下のもの | 地積に850円を乗じて得た額に298,000円を加えて得た額 |
| 500㎡を超え1,000㎡以下のもの | 地積に810円を乗じて得た額に318,000円を加えて得た額 |
| 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの | 地積に740円を乗じて得た額に388,000円を加えて得た額 |
| 2,000㎡を超え4,000㎡以下のもの | 地積に650円を乗じて得た額に568,000円を加えて得た額
|
| 4,000㎡を超えるもの | 地積に640円を乗じて得た額に608,000円を加えて得た額 |
(3)森林
主に森林として利用されている土地
| 地積の区分 | 負担金に係る算定金額 |
| 750㎡以下のもの | 地積に59円を乗じて得た額に210,000円を加えて得た額 |
| 750㎡を超え1,500㎡以下のもの | 地積に24円を乗じて得た額に237,000円を加えて得た額 |
| 1,500㎡を超え3,000㎡以下のもの | 地積に17円を乗じて得た額に248,000円を加えて得た額 |
| 3,000㎡を超え6,000㎡以下のもの | 地積に12円を乗じて得た額に363,000円を加えて得た額 |
| 6,000㎡を超え12,000㎡以下のもの | 地積に8円を乗じて得た額に287,000円を加えて得た額 |
| 12,000㎡を超えるもの | 地積に6円を乗じて得た額に311,000円を加えて得た額 |
(4)前(1)~(3)に掲げる土地以外の土地
200,000円
5.専門家の活用
(1)承認申請手続きを行う者
① 法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申 請手続きの全てを依頼する手続きの代理は認められない。
② 法定代理人による場合を除いては、申請手続きは申請者本人が行う必要があり、申請書に は申請者本人の記名、押印が必要となります。
③ 承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対して行われる。
(2)申請書等の作成に関する専門家の活用
① 申請手続きに関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。
② 申請者ご自身で申請書や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行 してもらうことができます。
③ 業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、 司法書士および行政書士に限られます。
なお、申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立っ て、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。
(3)実地調査へ同行する者
申請者は、申請の後、法務局担当管による実地調査における現地確認への協力を求められる場 合がありますが、申請者が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。
→ お問い合わせはこちら → 目次に戻る
お問合せ・ご相談はこちら

許認可申請サービス、会社設立サービス、相続・遺言手続きサービスについて、ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
| 受付時間 | 8:45~17:15 |
|---|
| 定休日 | 土日 |
|---|
担当:堀 宏一(ほり こういち)
東京都町田の堀宏一行政書士事務所では建設業許可、宅建業許可、産廃業許可、遺言・相続、会社設立、在留許可、成年後見などのお悩みを承っております。
小田急町田駅近くに事務所を構える行政書士が、町田市を中心に迅速に対応させていただきます。
| 対応エリア | 東京都町田市及び周辺 |
|---|
お気軽に
お問合せください
お役立ち情報
許可申請サービス
会社設立サービス
相続・遺言手続サービス
事務所紹介
町田・堀宏一
行政書士事務所
主な業務地域
東京都町田市及び周辺


